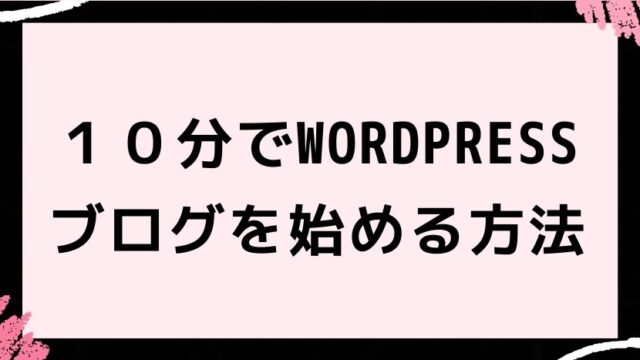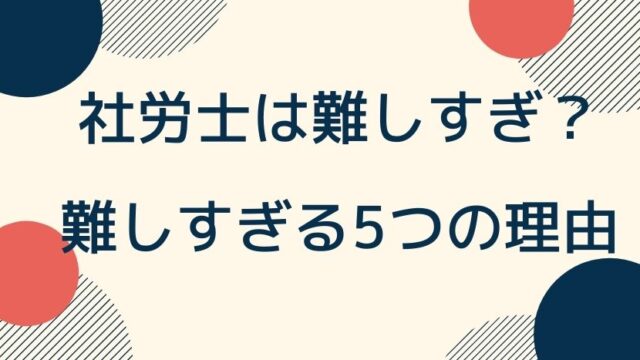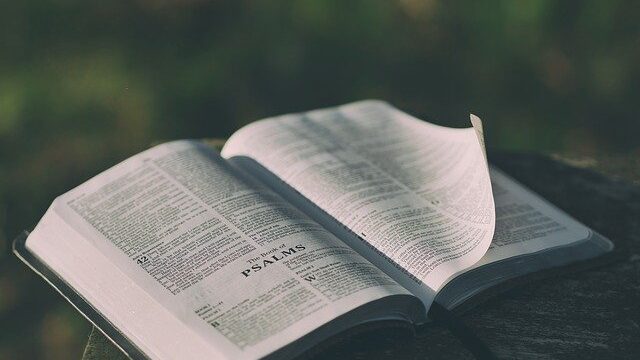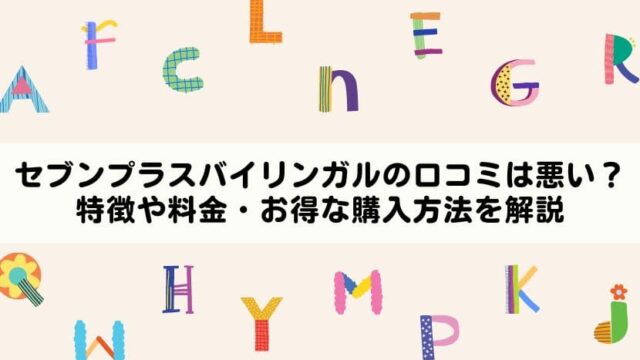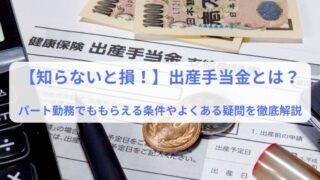2025年4月、育児・介護休業法の改正により、子の看護休暇の対象範囲や取得事由が大きく見直されます。制度をきちんと整え運用することで、従業員が安心して働ける環境をつくれるだけでなく、企業の信頼性や人材の定着率アップにもつながるでしょう。
とはいえ、具体的にどのような点が変わるのか、また企業としてどんな対応が必要なのか、不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、2025年の改正で子の看護休暇がどう変わるのか、そのポイントと企業が押さえておきたい実務対応について解説していきます。
子の看護休暇とは?基本をおさらい

子の看護休暇とは、「育児・介休業法」に基づく制度で、小学校3年生までの子どもを養育する従業員が、その子どもの看病や世話をするために取得できる休暇です。従業員から申し出があった場合、企業には休暇を認める義務があります。
取得可能な日数は、以下のとおりです。
- 子どもが1人の場合:年5日まで
- 子どもが2人以上いる場合:年10日まで
休暇の取得方法も柔軟で、「1日単位」に加えて、「半日単位」や「時間単位」での取得も可能です。ただし、たとえば午前だけ出勤して午後に一時的に退勤し、その後また出社するいわゆる「中抜け」の形での取得までは、企業に認める義務はありません。
なお、子の看護休暇は「年次有給休暇」とは別の制度です。そのため、子の看護休暇を取得しても年次有給休暇の日数には影響しません。
子の看護休暇は2025年の改正でどう変わる?3つのポイントを解説

2025年4月に「育児・介護休業法」が改正され、子の看護休暇にも変更がありました。では、具体的にどのような点が変わるのでしょうか。ここでは、主な改正ポイントを3つ解説します。
対象となる子の年齢が「小学校3年生修了」までに拡大
2025年4月の法改正により、子の看護休暇の対象となる「子どもの年齢」が拡大されました。
これまでは「小学校就学前まで」でしたが、改正後は「小学校3年生修了まで」、つまり9歳に達した年度の3月31日までが対象となります。
ただし、病気などの理由で就学が1年遅れた場合でも、「9歳の年度末まで」です。たとえば小学校入学が1年遅れた子どもについては、「小学校2年生修了時点」までが看護休暇の対象期間となります。
取得事由に「学校行事(式典等)」や「感染症による学級閉鎖」が追加
2025年4月の改正では、子の看護休暇を取得できる事由にも変更がありました。
これまでは「病気やけがの看護」などに限定されていましたが、改正後は「学校行事(式典)」や「感染症による学級閉鎖」なども新たに対象となります。
以下は違いをまとめた表です。
| 2025年3月まで | 病気・けが 予防接種・健康診断 |
| 2025年4月以降 | 上記に加えて、 感染症に伴う学級閉鎖など 入園式・入学式・卒業式 |
コロナ禍では、学校の突然の休校により、子どもの世話に困った従業員が多く見られました。その対応に追われた人事担当者の方も、記憶に新しいでしょう。
今回の改正により、学校保健安全法に基づく臨時休業や出席停止となった場合も、子の看護休暇の対象として認められます。
また、これまで入学式や卒業式などの学校行事には、多くの従業員が「年次有給休暇」を利用して対応していました。しかし今後は、子の看護休暇を使って取得することも可能になります。
労使協定で除外できる労働者範囲の見直し
2025年4月の改正により、子の看護休暇において労使協定で除外できる労働者の範囲が見直されました。
まず、改正前の除外対象を確認しましょう。
- 引き続き雇用された期間が6か月未満の労働者
- 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
上記のうち「1. 雇用期間が6か月未満」は撤廃され、今後は「2. 週2日以下の所定労働日の労働者」のみが除外対象となります。
たとえば、これまでであれば「入社2か月の従業員」は子の看護休暇の対象外となっていましたが、改正後は取得可能です。
子の看護休暇への対応で企業が取るべき実務対応策
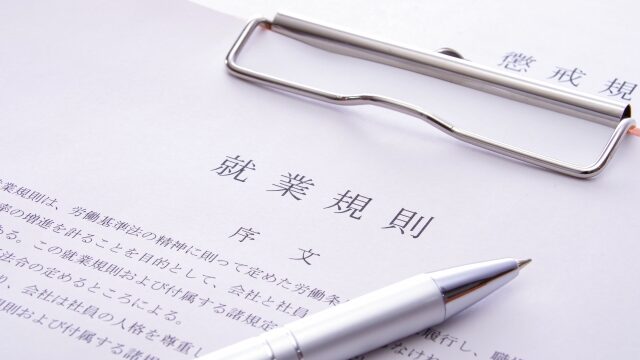
2025年4月の法改正により、企業には子の看護休暇に関する制度対応が求められます。ここでは、人事・労務担当者が押さえておくべき具体的な実務対策を4つ紹介します。
就業規則の見直しと労基署への届出
2025年4月の法改正により、子の看護等休暇について就業規則を見直す必要があります。
主な改正点は次のとおりです。
- 名称変更(子の看護休暇→子の看護等休暇)
- 対象となる子の範囲の拡大
- 取得事由の追加
- 労使協定による除外労働者の範囲の見直し
これらを踏まえ、就業規則を以下のように整備しましょう。(太字部分は今回の改正に伴う変更箇所を示すものです)
【就業規則例】
第◯条(子の看護等休暇)
1.小学校第3学年修了までの子を養育する従業員(日雇従業員を除く)は、次に定める当該子の世話等のために、就業規則第◯条に規定する年次有給休暇とは別に、当該子が1人の場合は1年間につき5日、2人以上の場合は1年間につき10日を限度として、子の看護等休暇を取得することができる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。
一 負傷し、又は疾病にかかった子の世話
二 当該子に予防接種や健康診断を受けさせること
三 感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話
四 当該子の入園(入学)式、卒園式への参加
ただし、労使協定により除外された、1週間の所定労働日数が2日以下の従業員からの申出は拒むことができる。
出展:厚生労働省 育児・介護休業等に関する規則の規定例(簡易版)
見直し後は、この就業規則の変更について、所轄労働基準監督署への届出も必要です。忘れず対応しましょう。
労使協定の修正・再締結
子の看護休暇について、取得できない労働者(除外対象)を定めている場合は、2025年4月の改正内容を踏まえて労使協定を修正・再締結する必要があります。
有効な労使協定とするには、以下の適切な手続きを踏むことが重要です。
- 労働組合(組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)と内容を協議する
- 使用者側で協定書を作成する
- 労使で協定を再締結し、締結日を記載のうえ双方の記名押印または署名を行う
労使協定を再締結したあとは、その内容を就業規則にも反映させます。
なお、労使協定は、労働基準監督署への届出は不要です。
従業員への制度周知
就業規則や労使協定は、変更や届出を行っただけでは効力を発揮しません。変更内容を従業員に周知して、はじめてその内容が有効になります。加えて、従業員がいつでも確認できる状態にしておく必要もあります。
ではどのように周知すればいいのでしょう。労働基準法では、以下のいずれかの方法で周知することを義務付けています。
| 方法 | 内容 |
| 常時各事業所の見やすい場所に掲示・備付け | 各事業所の休憩室や更衣室など誰でも見られる場所に置く |
| 書面で交付 | 就業規則の写しを従業員に配布する |
| デジタルで閲覧できるようにする | 社内サーバーなどで従業員がいつでも閲覧できる状態にする |
なお、以下のような例は「周知」とは認められませんので注意しましょう。
申請方法の見直し
制度は規定するだけではなく、実際に運用されてこそ意味があります。もし現在、子の看護等休暇の利用が少ない場合は、従業員が活用しやすいよう申請方法を見直しましょう。
例えば、以下のポイントが挙げられます。
| 申請を柔軟にする | 子どもの風邪やけがは突然です。当日の電話や口頭での申請を認め、書類は後日提出とする方法が有効です。 |
| 過大な証明を求めない | 診断書を求めることも可能ですが、従業員の負担になります。医療機関の領収書や保育園の連絡帳の写しなど、負担の少ない証明で対応しましょう。 |
| 管理職への研修を実施する | 制度をスムーズに運用するため管理職にも研修や説明をおこない、理解を深めてもらうことが重要です。 |
実際に使いやすい制度にすることで利用率が上がり、働きやすい職場環境の整備につながります。
2025年改正をふまえた子の看護休暇の注意点

これから子の看護休暇を実際に活用していくにあたり、どのような点に注意すべきなのでしょうか。ここでは、2025年の改正を踏まえた上で、特に押さえておきたい注意点を3つ紹介します。
「無給」でOK!賃金支払い義務はなし
今回の改正によっても、子の看護休暇について賃金の支払い義務は変更されていません。そのため、これまで通り無給で問題ありません。
実際に、厚生労働省の「令和3年度 雇用均等基本調査」によると、子の看護休暇を無給としている企業は65.1%にのぼり、有給(または一部有給)としている企業は34.9%にとどまっています。
ただし、有給扱いとすることで、従業員の満足度や会社への信頼感が高まり、人材の定着や企業イメージの向上につながることもあります。企業の方針や人材確保の観点から、賃金支給について検討する価値は十分にあるでしょう。
日常行事はNG!対象はあくまで「式典等」
今回の改正で、子の看護休暇の取得事由に入学式や卒業式などの「式典」が新たに追加されました。注意が必要なのは、対象となるのはあくまで「式典として行われるもの」に限られるという点です。
そのため、以下のような日常的な学校行事については、子の看護休暇を利用することはできません。
- 参観日
- 運動会
- 親子遠足
ただし、取得事由は法律で定められたものに加え、会社が就業規則で独自に追加することも可能です。こうした日常行事も対象に含めることで、従業員にとってより使い勝手の良い制度となるでしょう。
入社直後の従業員も取得可能
これまでは、入社6か月未満の従業員については、労使協定を結ぶことで子の看護休暇の対象から除外することが可能でした。しかし、今回の改正によりこの除外規定は撤廃され、入社したばかりの従業員でも子の看護休暇を取得できるようになりました。
例えば、入社してまだ1週間の従業員であっても、申し出があれば休暇を認める必要があります。
「子の看護休暇」と「年次有給休暇」では要件が異なるため、違いを正しく把握しておくことが大切です。
子の看護休暇の対応に不安がある場合は社労士に相談を

子の看護休暇に関する法改正への対応では、就業規則の見直しや労使協定の再締結、従業員への周知など、企業には多くの実務対応が求められます。
また、子の看護休暇は両立支援等助成金の対象にもなりますが、助成金は要件の変更が頻繁にあり、担当者が正確に把握し続けるのは大きな負担となるでしょう。
こうした中、運用ミスや認識不足が原因で、従業員との間にトラブルが発生するリスクも少なくありません。
そこでおすすめしたいのが、労務の専門家である「社労士への相談」です。
社労士から適切なアドバイスや実務サポートを受けることで、最新の法令や助成金制度にもきちんと対応しながら、安心して子の看護休暇を運用できます。一度依頼を検討してみてはいかがでしょうか。
子の看護休暇制度を正しく理解し、従業員が働きやすい環境づくりを

2025年の法改正により、子の看護休暇は「小学校3年生修了」まで対象が広がり、「学級閉鎖」や「入園・入学式、卒業式」も取得理由に加わりました。さらに、「入社6か月未満」の従業員も対象となり、これまで以上に多くの従業員が利用できる制度になります。
こうした改正にあわせて、企業には就業規則の見直しや制度の周知、申請手続きの整備が求められます。もちろん自社で対応することもできますが、助成金の活用や労務トラブルを防ぐために、社労士に相談してみるのも一つの方法です。
「子の看護休暇を整えたい」「もっと働きやすい職場にしたい」と感じたときは、ぜひ気軽に労務のプロである「社労士」へ相談してみてください。