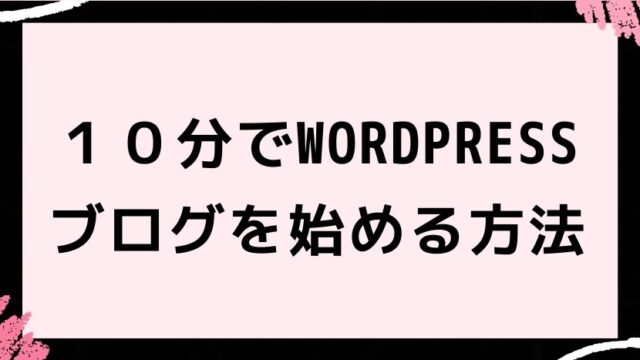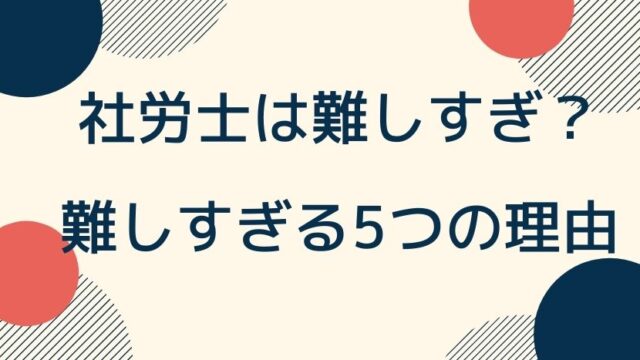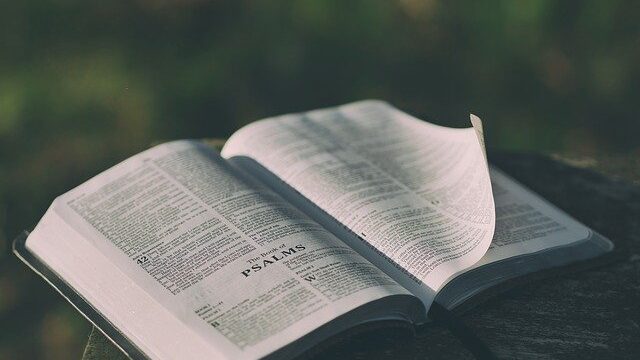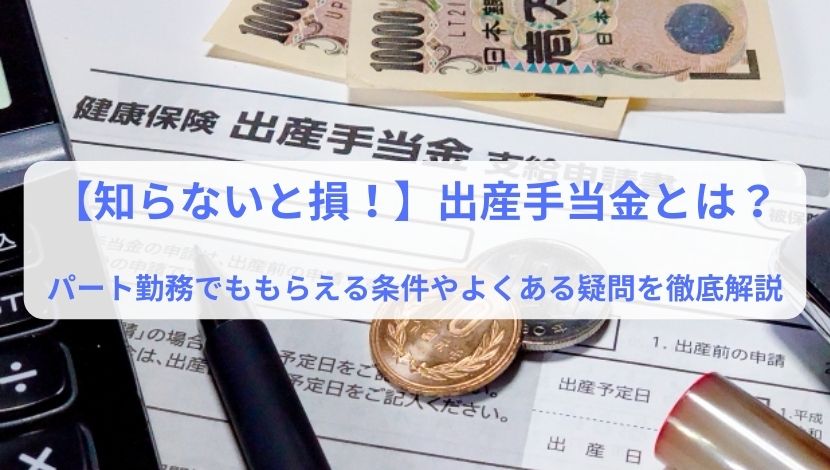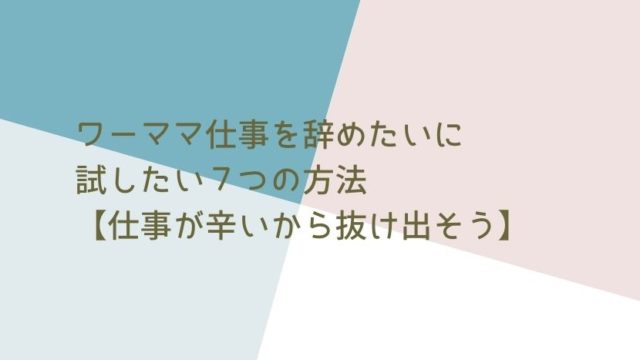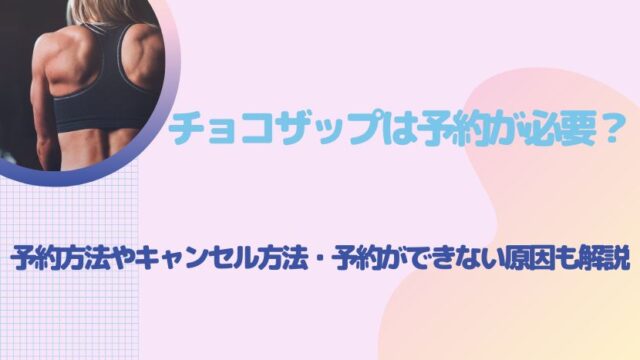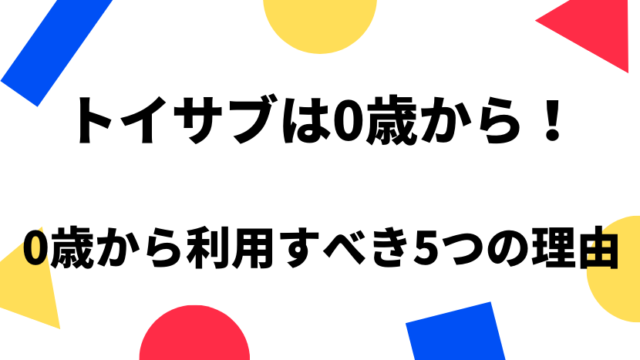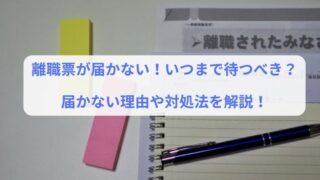出産手当金とは、出産のために仕事を休む間の生活をサポートしてくれる制度です。
正社員の制度とのイメージが強いかもしれませんが、実はパート勤務でも、一定の条件を満たせば出産手当金を受給できます。
とはいえ、以下のような疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。
- 勤続年数が短いけど大丈夫?
- 扶養内のパートでももらえる?
- 退職したあとでも受け取れるの?
本記事では、出産手当金の基本情報から、パート勤務者がもらうための条件、扶養・退職・申請方法に関するよくある疑問まで、わかりやすく解説します。
「もらえるはずだったのに知らずに損した…」と後悔しないために、ぜひ最後までご覧ください。
- 出産手当金はパート勤務でも条件を満たせば受け取れる制度
- 支給されるための3つの条件
- 扶養内・退職後・勤続年数など状況別の受給可否と申請の流れ
出産手当金とは?パート勤務者にも支給される制度

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ際に、健康保険から支給される給付金です。
労働基準法では、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間前)から産後8週間までの休業を、企業は認めなければならないと定めています。
ただし上記の期間は、賃金支払いまでを義務付けているわけではありません。そのため、産休中は無給となるケースが一般的です。
こうした収入の減少を補うために設けられているのが「出産手当金」です。
出産手当金は会社ではなく、健康保険(協会けんぽや健保組合など)から支給されるもので、産休中の生活を支える重要な仕組みとなります。
支給対象となる期間は、出産予定日の42日前(多胎妊娠は98日前)から出産後56日までのうち、給与が支払われなかった日数です。
出産手当金はパート勤務も対象となる!
出産手当金は「正社員だけがもらえる手当」というイメージを持たれがちですが、パート勤務であっても健康保険に加入していれば受給対象となります。
支給の可否を決めるのは雇用形態ではなく、健康保険の「被保険者本人」であるかどうかです。
つまり、会社の社会保険に加入しているパートであれば、出産手当金を受給できます。
以下で詳しく出産手当金がもらえる条件を確認していきましょう。
出産手当金とは?パートがもらえるための3つの条件

出産手当金を受け取るためには、次の3つの条件をすべて満たしている必要があります。
- 健康保険に加入していること(扶養ではなく本人加入)
- 産休中に給与が支払われない、もしくは少ないこと
- 妊娠4ヵ月(85日)以上であること
以下でそれぞれの条件について解説します。
条件① 健康保険に加入していること(扶養ではなく本人加入)
出産手当金を受け取るには、本人が健康保険に加入していることが条件です。
健康保険には、大企業などが運営する「健康保険組合」や、健康保険組合がない企業の従業員が加入する「協会けんぽ(全国健康保険協会管掌)」などがあり、これらの医療保険に加入していることが前提となります。
健康保険に加入できるのは正社員だけはありません。以下の5つの条件をすべてを満たすパート勤務者は健康保険に加入することができるため、出産手当金を受け取ることが可能です。
一方で、配偶者の健康保険に「被扶養者」として加入しているだけのパート勤務者は出産手当金の対象外です。たとえ出産のために仕事を休んでも、出産手当金は受け取れません。
つまり、出産手当金を受け取るには、「扶養内」ではなく「本人が健康保険に加入していること」が大前提となります。
条件② 産休中に給与が支払われない、もしくは少ないこと
出産手当金が支給されるのは、出産のために仕事を休んでいる期間に、給与が支払われていない、または支給額が出産手当金よりも少ない場合です。
出産手当金は「休業中の収入を補うための手当」です。もし産休中に通常どおりの給与が出ている場合は、手当を受け取る必要がないため、支給対象外となります。
ただし、給与が支払われていても、その金額が出産手当金の1日あたりの金額より少ない場合は、差額分を出産手当金として受け取ることができます。
このように、「完全に無給」である必要はなく、「出産手当金より少ない給与」の場合でも支給対象となることを理解しておくと安心です。
条件③ 妊娠4ヵ月(85日)以上であること
妊娠4ヵ月(85日)以上であれば、出産手当金を受給できます。
これは、健康保険制度において「出産」と認められるのが、妊娠4ヵ月以降の出産、早産、死産、流産、人工妊娠中絶などに限られているためです。
反対に、妊娠4ヵ月未満で流産した場合に休業しても、出産手当金の支給対象にはなりません。
妊娠4ヶ月以上であれば正常分娩だけでなく、死産・流産・人工妊娠中絶も含まれる点が、出産手当金の特徴です。
【条件別に解説】出産手当金とは?パートでももらえるかチェック
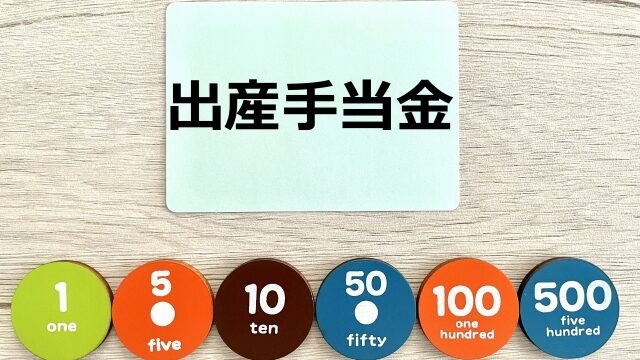
ここでは、よくある3つのパターン別に、パートでも出産手当金がもらえるのかどうかを解説します。
パート勤務1年未満の場合でも出産手当金はもらえる?
出産手当金には、「加入期間が◯年以上必要」といった要件はありません。
そのため、パートで働き始めて間もない場合でも、健康保険の被保険者として加入していれば出産手当金を受け取ることができます。
ただし、勤務期間が短い場合は、支給額に影響がある点に注意が必要です。
被保険者期間が1年未満の場合、出産手当金の計算には、次のうちいずれか低い方の金額が基準となります。
このため、同じ勤務条件でも、1年以上勤務している人よりも手当金の額が少なくなる可能性があります。
とはいえ、条件を満たしていれば出産手当金そのものはきちんと支給されるため、安心してください。
なお、出産後に受け取れる「育児休業給付金」は雇用保険から支給される別の制度です。育児休業給付金は、勤続1年未満の従業員については、労使協定により育休の対象外とされるケースがあるため、あわせて確認しておきましょう。
パートで旦那の扶養内だと出産手当金はもらえる?
パートで働いている方の中には、ご主人の扶養内で働いているという方も多いのではないでしょうか。
結論から言うと、扶養内で健康保険に加入しているだけでは、出産手当金はもらえません。
出産手当金は、健康保険の「被保険者本人」が出産のために仕事を休み、給与が支払われなかった期間に支給される休業補償です。そのため、被扶養者(扶養されている家族)は対象外とされています。
つまり、パート勤務であっても出産手当金を受け取るには、「扶養内」ではなく、自分自身が勤務先の健康保険に加入していることが条件となります。
受給を希望する場合は、まずご自身の健康保険の加入状況を確認しておきましょう。
パートを退職後にも出産手当金をもらえる?
妊娠をきっかけに、パートを辞めることを検討している方も多いのではないでしょうか。
「退職したら出産手当金はもらえないのでは?」と心配になりますが、一定の条件を満たしていれば、退職後も出産手当金を受け取れます。
これは「資格喪失後の継続給付」と呼ばれるもので、以下の2つの条件をどちらも満たしていれば、パートを退職しても出産手当金を受け取ることができます。
加えて注意が必要なのが、退職日に出勤している場合は支給対象外になる点です。
資格喪失後の継続給付を受けるには、退職日当日に出勤せず、完全に休業している必要があります。
出産手当金とは?パート勤務者の支給額と計算方法
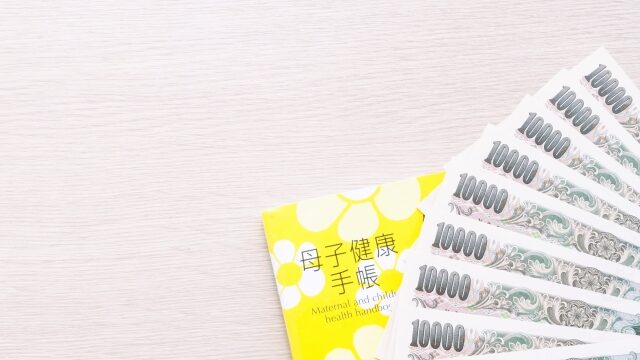
出産手当金の支給額は、健康保険における標準報酬月額をもとに計算されます。
標準報酬月額とは、社会保険料の計算を簡略化するために、被保険者の1カ月分の給与などの報酬を一定の範囲ごとに区分したものです。そのため、実際の「給与額」とは必ずしも一致しません。
出産手当金は1日につき、次のように計算されます。
たとえば、支給開始日前12か月間の標準報酬月額が10万円だった場合、計算は以下のようになります。
10万円÷30日✕2/3 = 約2,222円/日
この方が、産前42日+産後56日=合計98日間の出産手当金を受け取るとすると、2,222円 × 98日 = 約217,756円。
つまり、約21万円が出産手当金として支給されます。
出産手当金のおおよその額を知りたい方は「出産手当金計算ツール」を使うといいでしょう。
出産手当金の申請方法と手続きの流れ

出産手当金は以下の流れで申請します。
- 産休前に申請書をもらう
- 自分で記入する(被保険者記入欄)
- 産院で医師または助産師に記入してもらう
- 産休開始後に職場へ提出し事業主に記入してもらう
- 健康保険組合に提出
- 出産手当金の振り込み
① 産休前に申請書をもらう
まずは、勤務先の人事担当者や上司に「出産手当金の申請書がほしい」と伝えましょう。
申請書は、加入している健康保険組合(または協会けんぽ)から事業主を通じて交付されるのが一般的です。
② 自分で記入する(被保険者記入欄)
申請書を受け取ったら、まずは以下の自分の情報(被保険者欄)を記入します。
- 氏名・住所などの被保険者情報
- 振込口座情報
- 申請期間
- 出産予定日・出産年月日
- 出生児数など
③ 産院で医師または助産師に記入してもらう
次に、出産予定日や実際の出産日、出産児数などを記入してもらうために、申請書を産院へ持参します。医師または助産師が必要事項を記入し、押印してくれます。
申請書は、入院中に必要な書類となるため、忘れずに持参することが大切です。もし持参を忘れてしまうと、後日改めて郵送するなどの対応が必要になり、手続きに時間がかかってしまいます。
入院時には、母子手帳や診察券などと一緒に、「出産手当金の申請書」も準備しておくようにしましょう。
④ 産休開始後に職場へ提出し事業主に記入してもらう
出産手当金は、実際に休業してから申請するため、産休に入った後にもう一度申請書を職場へ提出します。
事業主が、就労状況や給与支給状況などを記入します。
⑤ 健康保険組合に提出
すべての記入が完了したら、出産手当金の申請書を健康保険組合(または協会けんぽ)へ提出します。
申請書には事業主の証明欄もあるため、職場が取りまとめて提出してくれる場合が多いですが、職場から受け取った書類を自分で郵送や窓口で提出するケースもあります。
不明点がある場合は、会社の人事担当者か加入している保険組合に問い合わせてみましょう。
出産手当金とは?パート主婦のよくあるQ&A

ここでは、出産手当金に関してパート主婦の方が特に気になりやすいポイントをQ&A形式で紹介します。
出産手当金は扶養に入るともらえない?
扶養に入っている場合、出産手当金は支給されません。出産手当金が健康保険の「被保険者本人」に対して支給される休業補償だからです。
そのため、夫の健康保険に扶養として入っているパート主婦は、たとえ出産のために仕事を休んでも出産手当金は受け取れません。
育児休業給付金とはどう違うの?
育児休業給付金は、育休中に賃金が支払われない、または減額された場合に支給される制度です。「雇用保険」の被保険者が対象で、男女問わず受給できます。
育児休業給付金の主な支給要件は、以下のとおりです。
一方、出産手当金は「健康保険」の被保険者が対象で、出産前後の休業中の収入を補う制度です。支給対象は出産する女性本人のみとなります。
両者は、保険の種類・支給対象・支給期間・申請書類などが異なるため、それぞれの内容を正しく理解しておくことが大切です。
出産育児一時金は併用できるの?
出産育児一時金と出産手当金は併用できます。
出産育児一時金は、出産にかかる費用を補助する制度で、健康保険または国民健康保険に加入している本人、またはその扶養家族が対象です。
支給額は以下のとおりです。
| ・産科医療補償制度に加入している医療機関で出産した場合 | 50万円/児 |
| ・未加入医療機関で出産した場合 ・産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週未満で出産した場合 | 48.8万円/児 |
対象となるのは、妊娠4カ月(85日)以上での出産です。流産・死産・中絶でも条件を満たせば支給されます。
一方、出産手当金は出産による休業中の賃金補償です。健康保険の被保険者であれば、両方の制度を受給することが可能ですので、忘れずに手続きを進めましょう。
出産手当金は国民健康保険の場合はもらえるの?
国民健康保険の場合、出産手当金はもらえません。出産手当金は健康保険に加入している方が対象であるためです。
なお、国民健康保険の場合でも「出産一時金」は受給できます。
まとめ:出産手当金とは?パートでももらえる制度を正しく理解しよう

出産手当金は、出産のために仕事を休んだ際に健康保険を通じて支給される給付金です。パート勤務でも、条件を満たせば受け取れます。
支給されるためには、以下の3つを満たしていることが必要です。
- 本人として健康保険に加入していること(扶養は対象外)
- 産休中に給与が出ない、または少ないこと
- 妊娠4カ月(85日)以上の出産であること
支給期間は、出産予定日の42日前(多胎は98日前)から出産後56日までのうち、仕事を休んだ期間。金額は、日給の約3分の2相当が支給されます。
もらえるはずの手当を受け取り損ねないよう、制度の内容を理解し、早めに準備しておきましょう。